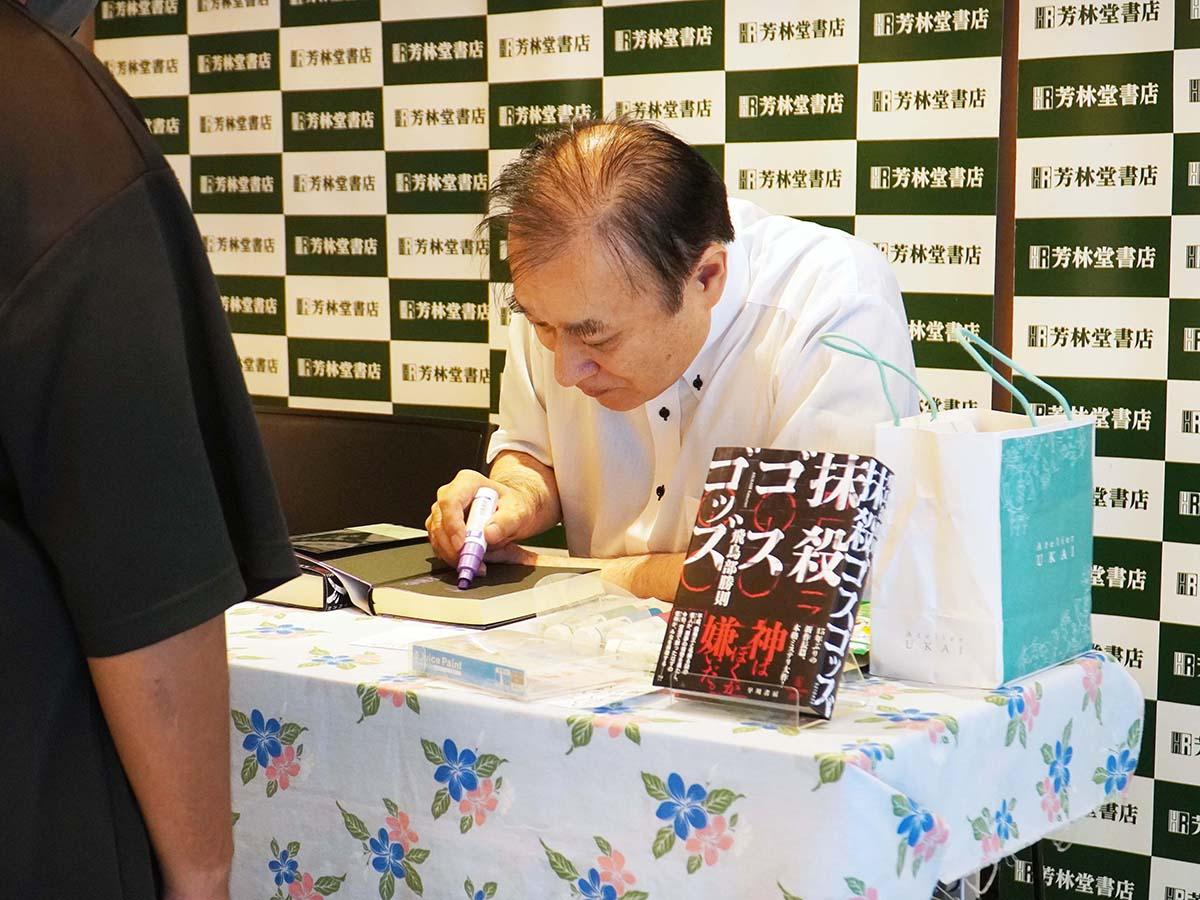穴八幡宮近くの「木組み博物館」が10周年 宮大工になりたい子どもの来館も

穴八幡宮の隣にある「木組み博物館」(新宿区西早稲田2)が11月3日、10周年を迎えた。
第1展示室の様子 その1(穴八幡宮の工法)=穴八幡宮近くの「木組み博物館」が10周年
清水建設などで長年、社寺や数寄屋など日本の伝統木造建築の施工管理に関わってきた谷川一雄さんが館長を務める同館。伝統工法で建築物を建てる人の減少、宮大工の後継者不足、材料の枯渇に伝統文化の危機を感じた谷川さんが、多くの人にその技術を伝え、次世代の技術者の発掘、育成に寄与するため、定年を機に開館した。
穴八幡宮の社殿や社務所、穴八幡宮隨神門などの再建に谷川さんが長年関わってきたことや、そのことで地元商店の人と人間関係があったこと、谷川さん自身が高田馬場出身ということもあり、現在の場所に決めた。海外からの来館者も多く、約3割が外国人で、これまで30カ国以上から来館があったという。地元の小学校や大学生から年配の人まで幅広い層が来館する。
木組みは、くぎや金物を使わずに切れ込みを入れた木をはめ合わせる工法。谷川さんが収集したり、制作を依頼したり、知人から提供を受けた実物の木組み、模型、道具を展示するほか、読み語りと谷川さんのミニ講座をする「木組みの森劇場」などのイベントも開催する。新宿区内の文化財や史跡、伝統産業を担う職人の仕事場を紹介する「新宿ミニ博物館」にも登録されている。
第1展示室(約17坪)は、木組みを中心に展示。米ヒバと台湾ヒノキで制作した「薬師寺三重塔(西塔)」の初重斗(しょじゅうと)組みの部分を約75%のサイズで再現した大型模型をはじめ、約30の木組み、約45本の丸太、約60種類の木の板を展示。木組みを手に取り、質感や重さ、匂いを体感できる。初重斗組みの展示を解体し、組み立てるイベントも過去に行った。第2展示室(約20.5坪)は、日本の伝統木造建築の仕上げ技術を中心に展示する。左官、鬼瓦、漆塗りの工程、彫刻とその彩色、茶室の模型などを紹介する。
10月には副館長の谷川一美さんとの共著「木組みの伝統技術-日本の誇る技と文化を伝える-」(理工図書)を出版。4000年の歴史がある木組みの技術、谷川さんが現場監督として得た経験、宮大工ほか職人との交流から学んだことなどを紹介している。
谷川さんは「孫が宮大工になりたいと言っていると祖父母の方が一緒に来館されたこともあった。もしかすると将来、宮大工になっているかもしれない。この博物館を未来にわたって残していければと思っている。10周年を記念したイベントにも取り組めれば」と話す。
開館日は火曜~木曜と月1回の土曜。開館時間は10時~16時。